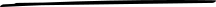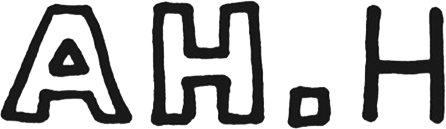PROFILE

編集者/株式会社グーテンベルクオーケストラ代表取締役。『コンポジット』『インビテーション』『エココロ』の編集長を務め、現在は出版物の編集・執筆から、コンサルティングを手がける。著書に『はじめての編集』『物欲なき世界』『動物と機械から離れて』等。下北沢B&Bで「編集スパルタ塾」、渋谷パルコで「東京芸術中学」を主宰。東北芸術工科大学教授。NYADC銀賞、D&AD賞受賞。

ファッションディレクター、スタイリスト。英国の雑誌『モノクル(MONOCLE)』の創刊より制作に参画、ファッションページの基礎を構築した。2015年には同誌のファッションディレクターに就任。2012年から2018年秋まで雑誌『ポパイ』のファッションディレクターを務めた。
写真と動画、WEBと紙。

フイナム:菅付さんが新著を出されたということで、今回はそのことを伺いつつ、いろいろなお話ができたらと思います。

菅付:昭雄さん、最近はどんな感じなんですか?

長谷川:今度、久しぶりに海外で撮影することになるかもしれません。

菅付:あぁ、ようやくそういうのが始まってくるんですね。

長谷川:そうですね。今、いろいろなブランドのビジュアルの仕事をさせてもらってるんですけど、コロナになってからはロケ場所は国内で、しかも換気のいいところでってなると、結構限られてきちゃってて。それがやっと緩和されてきたので、海外に行くことでビジュアルの見直しというか、立て直しみたいなことをしないとなって思っているところです。

菅付:そういうことも必要ですよね。

長谷川:はい。あとはコロナになって、紙をやめたりしていたんですけど、やっぱりWEBとかSNSの表現だけだと、写真の良さも伝わらないじゃないですか。

菅付:わかります。

長谷川:やっぱりプロダクトとして残さないと流れてしまうというか、使い捨ての情報になっちゃいますよね。ブランディングがしにくくなるなって。今回の菅付さんの本の話にも繋がると思うんですけど、やっぱり写真そのものの持つ意味というか、表現の幅みたいなことを色々と考えさせられます。

菅付:ですよね。基本的に今って動画全盛じゃないですか。動画が神様、動画がキングみたいな。

長谷川:本当にそうですよね。絶対に動画撮ってくれって言われますし。

菅付:若い子はInstagramかTikTokで、facebokとかtwitterを見てるのは、おじさんとかおばさんのオールドジェネレーションと言われてますね。

長谷川:(笑)。でもこれから変わっていくとは思います。僕はやっぱりスチール写真の方がファッションの表現には適してると思うんです。

菅付:完全に同意です。

フイナム:以前もその話をされてましたね。

菅付:結局、ファッションはクルマの広告とは違うということだと思うんですよね、今、全ての広告がクルマの広告みたいになってきていて。バキッと全方位から撮って、さらにパンフォーカスで全てにピントが合ってて、機能性が全部わかるような見せ方になっている。すごく面白くないです。クルマは広告を見る人の何十万人に1人が買うかどうかという世界だから、0.01パーセントぐらいに刺さればいいわけじゃないですか。だけどたくさんの人に届けなければいけないという幻想をもとに、ああいう説明的な表現をしているわけです。

長谷川:なんかわかる気がします。だってクルマの広告って、全部一緒に見えます(笑)。

菅付:そうですよね。でもファッションの表現は、ある程度リテラシーがないとわからない部分があるんですよね。これは言い方に気をつけなければいけないけど、どこか階級的で選民的なものというか。というのも、ファッションはイメージを“読む”という作業が必要なんです。

長谷川:うんうん。

菅付:ファッションの送り手はイメージを読ませるようなものを作らなければいけないし、受け手も見るのではなくて読むことが求められる。「あなたが言わんとすること、表現したいであろう美意識を読めました」という相互のコミュニケーションで成り立つものだと思うんです。だから解釈の余白とか説明しすぎないことが求められる。ファッション写真は、わからない人はわからなくていいという暗黙の了解があるんです。

長谷川:それはありますね。

菅付:動画の世界でも、技術的にもデータ的にもどんどんできることが増えてきてるから、尺も長くなるし、どんどん説明的になる。そうなるとイメージそのものや、コンセプト、美意識みたいなものを見たい、つまり読みたい人にとっては、うるさい表現ですよね。押し付けられてるような感じになるというか。それはファッションにはすごく向いてないと思います。

長谷川:あと、僕の場合は制作する側の人間だからか、映像を見たときに裏側のことを考えちゃうんですよね。スタッフは何十人もいたんだろうなとか、夜中までかかったんだろうなとか、あんまりおいしくない弁当食べてるんだろうなとか(笑)。

菅付:ファッション系の動画は色々見ましたけど、映画畑以外の人が作ってるもので面白いと思ったのは、少し前の〈BURBERY〉のやつだけですね、

長谷川:なんか飛んだりするやつですか?

菅付:そうそう。飛んだり雪が落ちてきたり。

長谷川:あれはすごいですよね。

菅付:フランスのチームが制作した動画なんですけど、やっぱり表現の柱がある人が動画をやると面白いですよね。そういうものがなくて、なんとなく撮ってるものは大体面白くない。前にも言いましたけど、スチールの良さは止まっていて動いてないことです。ダヴィンチの「モナリザ」は笑ってるのか悲しんでるのか、解釈の余地があるからこそ、どういう心情なんだろうってみんなが思うわけじゃないですか。あれが動き出してニコニコしたり悲しい顔をしたら、まるで面白くないと思うんです。

長谷川:捉え方の自由さというか、幅みたいなことですよね。余白というか。電源がないと見れないっていうのが、今の時代の不便さだったりしますよね。本とかたまに見るとすごく落ち着くんです。やっぱり長い歴史のある媒体だからこそなんでしょうね。

フイナム:で、こういう話をWEBでしているわけですが(笑)。

菅付:今はデジタルデバイスがメインだから、それは仕方がないんですけど、でもWEBとかデバイスはあんまり見すぎない方がいいと思います。

長谷川:そうですよね。あと、この「AH.H」はWEBマガジンですけど、WEBまで見てる人ってすごく少ないと思うんです。みんなインスタで見て終わってる。情報は無料で受け取るのが当たり前だし、しかもよりイージーな状態で受け取りたい。でもそれが例えば雑誌だったらお金を払わないと見れないわけで、お金を払ってまで知的要求を満たしたいと思う人というのは、ちょっと違うジャンルの人だと思うんですよね。そう思うと、何らかの刷物を作った方がいいのかなって思うんです。少しハードルの高いところにある情報を作っていくことで、本当にファッションが好きな人に、写真やロケーションという情報も込みで伝えられるんじゃないかと思うんです。というのは、僕の周りの友達は、ほとんどインスタをやってないんです。やってる人もいるけど、それはほんの一握り。みんなインスタ映えしない、地味だけど洒落てる服装をしてます。そう思うと、インスタ上のファッション好きな人のファッションと、ファッション業界のなかの一部の人のファッションって別物で、服装だけではなく、そこに至る所以である価値観も別物だと思うんです。モードこそがファッションだという人、〈UNIQLO〉でいいやと思う人、〈UNIQLO〉もいいけど他もいいよって思う人とか、いろいろな人がいますよね。その違いをきちんと見定めていかないといけないのかなと。ファッションを一括りにしてしまっても意味がないですから。その少ないゾーンのなかにいる人と、しっかり繋がっていきたいと感じます。

フイナム:今年の課題ですね。

菅付:ただ、無料で情報を取るということに、みんなが相当慣れてしまっているので、前とは違う工夫が必要ですね。お金を払うことに慣れてなくて、「今までずっとタダで見てたんですけど…」という感じだから、そこをどうするか。あとはやっぱり日本は景気が悪いので、若い人の可所分所得が下がってるというのは紛れもない事実です。そのなかで、ファッションとかカルチャーのコンテンツにお金を払ってもらうためには、作る側も相当頭を使わないといけないと思います。
写真の現在位置、可能性とは。

フイナム:そろそろ本のお話に移ろうと思うんですが(笑)。本書には数多くの海外の写真家が登場しますが、コロナ以降はskypeやZoomで取材されていたそうですね。

菅付:そうなんです、残念ながら。これがなかなか難しかったですね。何が難しいって、オンライン取材はどうしてもフレンドリーな感じにならないんです。『コマーシャル・フォト』でやってたこの連載って、直接会って取材することを前提とした企画だったんです。だからAlasdair McLellan(アラスデア・マクレラン)とかJamie Hawkesworth(ジェイミー・ホークスワース)、Harley Weir(ハーレー・ウィアー)、みんなに会ってきました。自腹でニューヨークとかロンドンに行っていたのですが。そしたらコロナになって海外に行けなくなり、Zoom取材が基本になりました。すると、向こうもやっぱり話しにくいわけです。

フイナム:たしかにオンラインでのインタビューは、相当やりにくいですよね。

菅付:そう。向こうも会ったこともない日本人から、長い時間インタビューを受けるわけで、なかなか大変です。でもそういうことをなんとか乗り越えて取材をしていたんですけど、文字校正の段階になって英訳して送ると、まぁ直しが多いんです。対面で取材していたときの3倍くらいの直しがくる。とにかくフレンドリーじゃないんですよね。

フイナム:目に浮かぶようです。。

菅付:それでもなんとかいい感じに掲載ができて、今回書籍に再録したいと連絡をすると、結構な人数に断られました。だってあなたのことよく知らないし、みたいな。

長谷川:それは大変ですね。。取材には何年ぐらいかけたんですか?

菅付:今回のものは6年ですね。以前出したものが5年分なので、連載は11年やってました。

長谷川:このキャスティング、毎回大変そうです。

菅付:大変でしたね。連載の最終回に写真家の杉本博司さんに出ていただいたんですけど、杉本さんには連載が始まったときぐらいからずっとオファーをしていて。それでようやく最終回だったらいいですよって言ってくれて。

長谷川:毎月ですよね、これ。月刊誌でやるような内容じゃないですよね。


フイナム:『写真が終わる前に』というタイトルはご自身でつけられたんですか?

菅付:はい。前作が『写真の新しい自由』で、今回も当然“写真”はつけるつもりだったんです。で、さっきお話しした杉本さんがご自身のことを語っている形容詞があって、それが“最後の写真家”なんです。それが少し頭にあって、あとは写真の終わりということについて考えることもあったので、こうなりました。

長谷川:すごくいいタイトルですよね。

菅付:コンテンツの中心が動画になってきているなかで、今写真にはどういう価値や可能性があるんだろうと。写真家、編集者、グラフィックデザイナー、アートディレクターなんかは、そういうことを考えざるを得ないと思うんです。この仕事はスチールが中心なのか、ムービーが中心なのか、両方なのか? 両方だった場合、どっちが比重が高いのか。

フイナム:確かに。

菅付:そしてムービーが中心だったら、そこで必要なのは写真家なのか、DP(Director of photography=撮影監督)なのか。というのも、スチールの写真家はもういらないよということが実際増えてるんです。こういうときだからこそ、写真にはもしかしたら価値がなくなっていて、本当に終わったりするのか、というのを考えた方がいいタイミングだと思います。

長谷川:すごくよくわかります。動画の現場って、基本的に時間がすごくかかるので、動画で色々やった合間にスチールを撮ったりするんですよね。なんならご飯を食べてる間に撮ってくださいとか言われたりして。おまけみたいな感じなんですよね。

菅付:あと1時間で撤収するので、それまでにスチールお願いします、みたいなこともありますよね。みんな嘆いてます。

長谷川:そう。なんかひどいなって思って。。結局みんな、お金のことしか考えてないんですよね。動画って単純に経費がかかるじゃないですか。スタジオを使うにも同じ場所だって動画の方がお金がかかりますし。で、お金がかかってることほど大事なものという風にみんな勘違いしてるんです。スチールはある意味では簡単に撮れてしまうから、格下に扱われてしまうというか。

菅付:わかります。

長谷川:けど、よく考えると、動画よりもスチールの方が見られるチャンスは大きいと思うんです。

フイナム:動画は最後まで見てもらうのに、ハードルがありますよね。

長谷川:そう。さっきスチールは簡単に撮れるみたいなことを言いましたけど、実際に撮り始めたらすごく時間がかかるはずで、直しもいっぱい出てくるわけです。一方で動画って、ババっと撮って「オッケー! 次はこっちから!」みたいな感じで進めたりもしますよね。だから根本的に全然違う世界なんですよね。なのにスチールをすごく軽んじてるなと思うんです。だからこの本のタイトルの重みをすごく感じました。

菅付:そうなんですよね。

長谷川:あと最近、デバイスが小さいために写真の良さが全く伝わらなくて、何をやってるんだろうって思うときが多くて。小さいデバイスだとどうでもいい写真も、いい写真も同じに見えちゃうし、なんか説明写真を撮ってるような気持ちになるというか。だんだんこんなことをやりたいわけじゃない、ちょっと違うよなと思ってきたんです。本当、考え直さないといけないことがたくさんありますね。

菅付:この連載をしているなかで、そういう写真の終わりみたいなことについて語っている人があちこちにいました。悲観的な意見を持ってる人もいるし、楽観的な希望を持ってる人もいますけど、僕は半分半分という感じですね。デバイスのデジタル化は止めようがないので、仕方ないなと思うんですけど、一方で写真の良さというのは見る方が主体的に読むということですよね。

長谷川:うんうん。

菅付:映像は、基本的には自動的に流れてきて受動的に見るもので、読み手の都合で可変できないですよね。一方で写真は見るだけではなくて、読むということができるわけです。見る方が主体的に参加して、自分のペースで主体的に読むことができる写真は、ものすごく素晴らしいメディアだと思います。

長谷川:そういうことをみんなが理解するようになると、もっとスチールでやろうっていうことになるんですかね?

菅付:そうなってほしいなと思います。ファッション広告のことを考えても、今は全体的に面白いファッション広告が減ってしまったとは思うんです。でもたまに、なぜこのモデルで、なぜこの服で、なぜこんな撮り方をしてるんだろうというものもあるんですよね。そういうことを意図的にメジャーな場でやってるのが、David Sims(デイビット・シムズ)とかMert and Marcus(マート&マーカス)です。「これ、君はわかりますか?」という写真を撮っている。つまり客に対して知能テストみたいなことをやってるわけですよね。痒いところに手が届くように、全部説明するようなものが良しとされてる時代において、なにこれ?というものがファッション写真にはまだあるじゃないですか。そういうものがある限りは、ファッション写真は大丈夫だと思うんです。

長谷川:なるほど。

菅付:そういう表現は読む方のリテラシーを信頼してないとできないわけで、つまり知的に挑発してるということは、ある程度逆に信頼しているということなんです。だから全部説明してますというのはコミュニケーションとして、非常に受け手を馬鹿にしていることだと思うんです。
変わりゆくファッションマーケット。

フイナム:最近のファッション業界の動きは、菅付さんにはどう映りますか?

菅付:まず全体的にファッション広告がコンサバ化してますよね。それには当然理由があるんですけど、よく言われているのは今までファッションマーケットではなかったところのマーケットがすごく大きくなったということです。具体的に言うと中国と中近東。ラグジュアリーブランドも『VOGUE CHINA』とか『ELLE CHINA』にバンバン出稿してますよね。

フイナム:そうですね。

菅付:そうなると、性的な表現やポリティカルな匂いがあるもの、あとは反体制的な匂いがあるものは出せないわけです。それまで反体制とか、エロスとかポリティカルなものって、ファッション表現において最高のスパイスだったわけです。でもそうしたものは中国のメディアには絶対に出せない。あとは中近東だと同性愛っぽいものにはものすごく厳しいですよね。つまりエッジのある表現に対して、不寛容なマーケットが大きくなってしまったということです。

フイナム:なるほど。

菅付:一方で、最近「world without china」という言葉を聞くようになりました。今は中国の人があまり海外に行けないじゃないですか。そしてこのコロナで「Made in China」も随分減りました。だから中国なしでも、あらゆるビジネスをやっていけるようにしようというのが、今の欧米先進国のキャッチフレーズになっています。

長谷川:少し前にニュースで見たんですが、中国で化粧品を売るのに、全ての成分表示と配合率を提出しなければいけないっていう話で。普通に考えてそんなことできるわけないじゃないですか。自社だけの情報があるからこそ個性が存在できるのに、公開してしまったらどうぞパクってくださいって言ってるようなものですよね。でもどうやら、中国の売り上げが大き過ぎて、みんなやらないわけにいかないかもってなってるみたいで。

フイナム:それはあまり健康的な状態ではないですよね。

菅付:もう1つ、中近東にも巨大なマーケットがあるわけですが、この前カタールでサッカーのワールドカップがあったじゃないですか。あれで性的表現に関しての規制が少し緩くなったんですよね。ゲイが御法度とかって言ってたら、サッカー選手でゲイの人だっているわけだし、ワールドカップなんかできないわけで。だからいろいろなことが少しづつ変わってきてはいると思います。

フイナム:ブランドの広告表現でいうと、〈BALENCIAGA〉に注目している人は多いですよね。

長谷川:あぁ、面白いよね。

菅付:そうですね。でもこないだ炎上しちゃって、今ちょっと逆風ですよね。〈GUCCI〉も(アレッサンドロ)ミケーレが辞めて。

長谷川:ミケーレはなんでやめたんですかね?

菅付:単純に売り上げが伸びなかったからだと思います。まぁそもそも「KERING」グループの売り上げ目標がものすごく高いということもありますが。

長谷川:日本人の若い子とかを見てると、みんな〈GUCCI〉とか好きそうな感じですけどね。テイストだけピックアップして〈GUCCI〉で買ってないんですかね。

菅付:デムナ・ヴァザリアとアレッサンドロ・ミケーレは、間違いなくスターデザイナーだし、ここ10年ぐらいの大きな流れを作った人ですよね。ただこの1年でものすごく潮目が変わりましたよね。ラフ・シモンズも自分のブランドをやめましたし。

長谷川:あれはどういうことなんですかね。

菅付:どうなんでしょうね、〈PRADA〉に専念するということなのか。

長谷川:〈PRADA〉はお店に行って、実際の商品を見ると面白いんですよね。ラフっぽいものと、ミウッチャ(プラダ)っぽいものが混ざってて。見ててわかるんです。同じLサイズなのにサイズ感が全然違うものが同じ部屋で共存している。そこが今の〈PRADA〉は面白いですね。〈BALENCIAGA〉は広告と繋がった商品づくりをしていて面白いと思います。

菅付:攻めてますよね。

長谷川:〈adidas〉とのコラボレーションの広告もオフィスで撮ったりしてて、その表現の仕方もなんか絶妙で面白かったですね。意外とそういう広告ってなくて、すごく考えながらやってることがわかったし。ああいうのが終わってしまうのは残念ですね。
写真が終わる前に
定価:¥2,200
仕様:四六判・並製・銀の特殊インクのカバー・帯あり
頁数:巻頭カラー口絵16ページ、本文280ページ、合計296ページ
ブックデザイン:BOOTLEG
発行・販売:玄光社
その2に続きます。