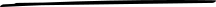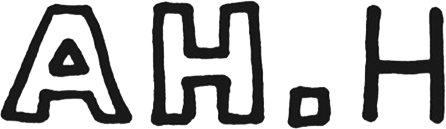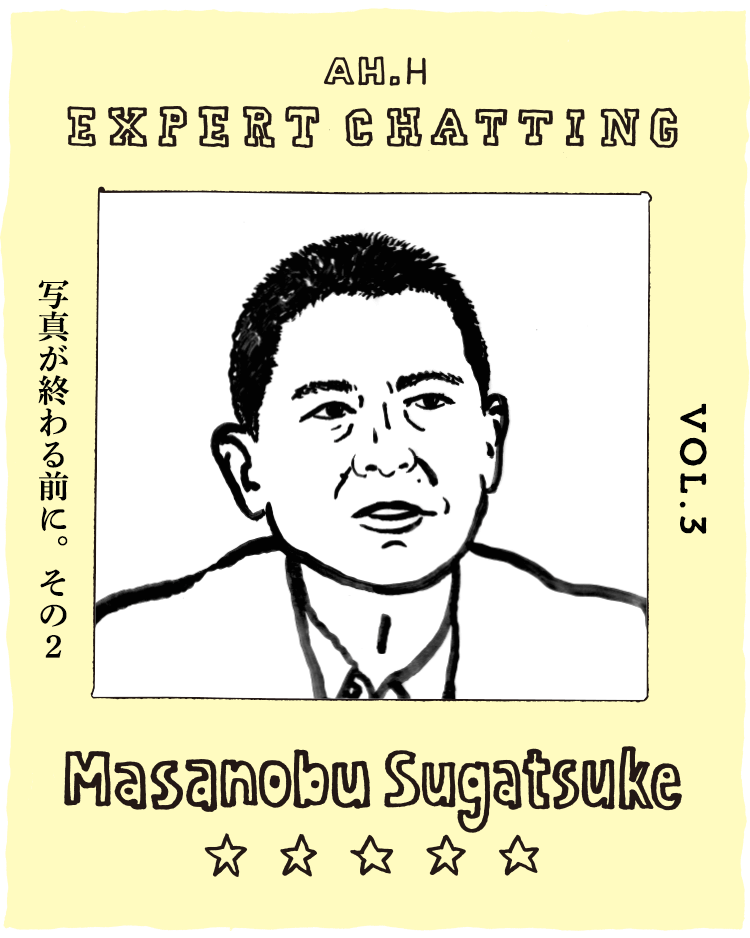PROFILE

編集者/株式会社グーテンベルクオーケストラ代表取締役。『コンポジット』『インビテーション』『エココロ』の編集長を務め、現在は出版物の編集・執筆から、コンサルティングを手がける。著書に『はじめての編集』『物欲なき世界』『動物と機械から離れて』等。下北沢B&Bで「編集スパルタ塾」、渋谷パルコで「東京芸術中学」を主宰。東北芸術工科大学教授。NYADC銀賞、D&AD賞受賞。

ファッションディレクター、スタイリスト。英国の雑誌『モノクル(MONOCLE)』の創刊より制作に参画、ファッションページの基礎を構築した。2015年には同誌のファッションディレクターに就任。2012年から2018年秋まで雑誌『ポパイ』のファッションディレクターを務めた。
撮影現場、悲喜こもごも。

フイナム:近いうちに海外に行く予定はありますか?

菅付:いまのところないですね。本当は去年11月に韓国の出版社に呼ばれて、僕の韓国版の本のプロモーションに行くはずだったんですけど、以前に比べて飛行機代がすごく高くなってしまったみたいで、なかなか行けなくなってます。

長谷川:昔は韓国は国内旅行ぐらいのノリでしたよね。

菅付:そうですよね。今は韓国の物価も上がってますしね。韓国は1年ぐらい前かな、政府の行政指導で賃金を上げましょうという働きかけがあったんです。

フイナム:日本でも〈ユニクロ〉が給料を上げるなんていう話もありましたよね。

菅付:そうそう。それで韓国は人件費がかなり上がったんです。韓国企業が儲かった分を全部社員に吐き出しなさいという政府の指導なんですね。そしたら韓国の飲食店とかの値段もかなり上がったたんです。だから韓国では物価が爆上がりで。

長谷川:売り上げがいい会社は、給料上げたらいいと思うんですけど、でもそうでもない会社ってそんなに上げられないですよね。日本はそういう意味では、まだ国が頑張ってるのかなって思うんです。物価が言うほど上がってないじゃないですか。だから意外とみんな普通に生活できてたりするというか。

菅付:日本の労働者がおとなしいんだと思いますね。前回話した日本映画の現場の件にしたって、ものすごく過酷ですよね。みんなこんな弁当食べてるんだ、と思ったりします。昭雄さん、日本映画の撮影現場に行かれたとことありますね。

長谷川:ないんです。

菅付:もちろんいい現場もあると思うんですけど、よくないところは過酷です。本当に好きじゃないとできないですよね。

長谷川:正月に本棚を片付けてたら、黒澤明の特集をしてた雑誌を見つけたんです。黒澤明の現場ってすごいって言うじゃないですか。もう本当に大変だったんだろうなって。でも、それでも付いていきたいって思わせてたわけだからすごいですよね。

フイナム:たしかに。監督の作るものに信頼があればこそですよね。

菅付:それはありますね。僕が実際に見た日本映画のロケ現場では、100人くらいがみんなすごく具材の少ない弁当を食べているんですよ。しかもあったかかったらまだいいですけど、冷えてるわけで。

長谷川:僕らの普段の撮影現場って、トモちゃんって子にお弁当を作ってもらってるんです。それに慣れるともう他のお弁当を食べられないんですよね。。やっぱり仕事が丁寧で美味しいし。だからたまに動画の現場とかに行くと…。

フイナム:それはキツいかもしれませんね。。

長谷川:しかも演者も同じお弁当だったりするんですよね。

菅付:そうそう。日本映画もそんな感じです。もちろんある程度予算がある作品とか、本当にスターみたいな人は別ですけど、インディーズな作品はみんな一緒の弁当を食べたりする。これを数週間やっていて、豊かな画面が撮れるのは難しいと思いましたね。

長谷川:本当ですよね。そういう辛い役柄だったらいいんでしょうけど(笑)。

菅付:そうそうそう(笑)。食事の話で言うと、僕が最初に自分中心でやった海外ロケがパリで、 写真家は七種諭(さいくささとし)さん、スタイリストが水谷美香さんだったんです。僕が編集・発行をしていた『コンポジット(composite)』という雑誌での撮影でした。そのときに水谷さんから「どんなにお金がない撮影でも、食事だけはケチらないでね。ギャラを安く抑えててもいいし、スタジオが小さくてもいいけど、食事を削っちゃうとまずいから」と言われたんです。それで予算がないわりにはいいケータリングにして、安いボトルワインを何本か入れたりして。そしたら現場はすごく楽しくなりましたね。やっぱり食事は大事だなと思いました。
改めてのブルース・ウェーバー論。

フイナム:菅付さんはいろいろな写真家と仕事してらっしゃいますし、本当にたくさんの写真を見ていると思うんですけど、そもそもどんな写真が好きなんですか?

菅付:「一番好きな写真家は誰ですか?」と聞かれて即答できるのはブルース・ウェーバーですね。

長谷川:僕もです。

菅付:ブルース・ウェーバーは写真集の作り方がうまいんですよね。彼の写真集は何度でも見返したくなるし、ずっと取っておきたくなる。

長谷川:たしかに。

菅付:写真のプリントを収めているだけじゃなくて、写真集がひとつの物語みたいになっていて、すごく愛蔵本的なものになってますよね。写真集をまとめていく力がウェーバーはすごいなっていつも思います。

長谷川:ダイジェストなはずなのに、ダイジェストじゃないというか。

菅付:そう! その通りです。

長谷川:バラバラなはずなのになんかストーリーがありますよね。人をきちんと捉えてるけど、ファッションも伝わってくる。そういうカメラマンって意外といないですよね。

菅付:すごくエターナルな感じがするんですよね。いつの時代に撮っても永遠な感じ。それはモノクロが多いというのもあると思うんですが、あとは好きな男性像、女性像があまり変わらないですよね。男性だったら髪をきっちり固めて、ちょっとフィフティーズみたいな感じ。女性だとちょっと昔のハリウッドグラマーな感じのが好き、という世界観がしっかりしてる。あと仕上がりが暖かいですよね。

長谷川:そうですね。

菅付:あの感じがすごくいいなと思うんです。

長谷川:あとあんまりドロドロしてないというか、ウエットな感じはないですよね。そこも心地いいのかもしれないです。ピーター・リンドバーグとかになってくると、人っていうよりも服というかファッションっていう感じですよね。あれはあれで好きなんですけど、ブルース・ウェーバーは、人の暖かさみたいなところがありますよね。

菅付:そうですね。リンドバーグも大好きですけど、彼の場合はもっと構築的で、形・光・動きに関してすごく厳密なんだと思うんですよね。だから絶対にかっこいいし、絶対にいい光を捉えてる。このモデルだったらこっちの向きがいい、みたいなことがはっきりしてる。ウェーバーはもうちょっとウォームで、被写体が持ってる弱いところとか、強がりなところもうまく捉えてるんですね。

フイナム:改めてブルース・ウェーバーに触れてみたくなります。

菅付:この10年間ぐらいで大人気のロンドンのアラスデア・マクレランは、ブルース・ウェーバー的ですよね。彼はもっと穏やかでもうちょっと繊細な感じですけど、暖かい光の感じが似ています。けど、彼はトワイライトタイムというか、マジックアワーでなるべく撮るんですよね。そこはウェーバーとは違いますね。

長谷川:個人的にはですけど、海外の雑誌を見てるとブルース・ウェーバーの写真とかが入ってないと、ファッション的な視点が強すぎちゃって、見ててキツいなって気がしちゃうんです。落ち着かないというか。ファッション業界にいるから、特にそうなのかもしれないですけどね。違う視点が欲しくなるというか。

菅付:そうですね。スタジオで撮って服が綺麗に見えている写真はファッション誌には絶対必要で、だからデヴィッド・シムズとかスティーブン・マイゼルみたいな写真家が必要とされると思うんです。一方でウェーバーのような、服よりも人寄りで、ちょっとストーリー感があって、ある種の疑似旅行記のようなものはファッション誌のいいエンターテイメントだったと思うんです。そういうのがちょっと減ったのは事実ですよね。
写真家という生き物。

フイナム:白川(青史)さんの写真は、長谷川さんから見て変わりましたか?

長谷川:いや、あんまり変わらないかな。白川くんってすごく綺麗好きなんだと思う。だからこれを撮ってくださいって言ったら、まずは全体像をちゃんと撮りたい人というか。そこはずっと変わんないかも。でもそれが彼のいいところなんだよね。やっぱりちゃんと捉えてくれるし、写真にシズル感みたいなのがあるし。

菅付:白川さんは画角、構図力が抜群ですよね。

長谷川:そうですね。トリミングするときも必ず白川くんにやってもらうんです。

菅付:うんうん。商業写真家は構図力がないと難しいですよね。構図力のない人は何をやっても無駄です。ドキュメンタリーの人はなくてもやっていけると思うんですけど。

長谷川:たしかに。白川くんの画角は好きですね。きっちり撮ってる感じが。

菅付:あと、昭雄さんと白川さんのコンビのやつはすごく軽やかというか、楽しそうな仕上がりになってて、それがいいですよね。

長谷川:ありがとうございます。

菅付:今は緊張感を与える写真が、全体的に好かれてない感じがします。90年代後半から2000年代くらいまではそういうのが結構あったんですけど。具体的に使うとスティーブン・クラインみたいな。緊張感があってライトがすごくダークで、モデルも辛そうな顔をしていて。そういったものは今は合わなくなってきましたよね。トム・フォードのときの〈GUCCI〉なんかにはすごく向いてる写真だと思うんですけど。

長谷川:スティーブン・クラインもトム・フォードも実はすごく好きなんですけど、スティーブン・クラインみたいな写真って、どうやったら撮れるんだろうって思っちゃいます。自分のなかに全くないので。

菅付:僕は本人に2回会ったことがあって、代官山でインタビューしたこともあります。物静かな人でしたね。いろいろな評判を聞きましたけど、まずはとにかく撮影が長いと。

長谷川:あー、長そうですね。

菅付:ずっとファインダーを見ていて「違う。違う。違う」とずっと指示してるんだって。その内、スタッフも何が違うのかわからなくなってくるらしくて(笑)。

長谷川:前に見たんですけど、『VOGUE』の別冊みたいなのをスティーブン・クラインが全部撮ってるストーリーがあって。プールサイドでダッチワイフが出てきたりして。

菅付:あぁ、その二つは大好きですよね。

長谷川:ライティングも、色々あってぐちゃぐちゃで。なんかもうすごかったですね。たぶんものすごくたくさん撮ったなかから選んでるんだろうなって。じゃなきゃ無理だろうって思いました。

菅付:スティーブン・クラインといえば、『ネオン・デーモン』っていう映画知ってます? ニコラス・ウィンディング・レフンが監督して、エル・ファニングが主演でファッションモデル業界を舞台にしたアート映画なんです。そこに完全にスティーブン・クラインをモデルにした写真家が出てくるんです。顔も出立ちもクラインそっくりで、ものすごく気難しくて注文が多くて、人に緊張感を与えるっていう(笑)。

長谷川:笑

菅付:そのシーンを観て、映画館ですごく笑っちゃいました(笑)。これはスティーブン・クライン的なファッション撮影が、いかに地獄かというのを表した映画ですね。この映画を観ると、ファッションモデル志望の女の子は、その夢をやめちゃいそうですよ。でも、スティーブ・クラインの写真は全然嫌いじゃなくて、彼じゃないと撮れない写真を撮ってるなとは思います。ただ、最近はスティーブ・クラインもだいぶ地味になっちゃいましたね。ちょっと今の時代の感じとは合わないんだと思います。

長谷川:あぁ、そうですか。

菅付:やっぱり写真があまりにもダークで、楽しそうじゃないですよね。それこそトム・フォードの〈GUCCI〉がかっこよくメジャーに見えてたときと、今は違うじゃないですか。〈GUCCI〉も(アレッサンドロ)ミケーレになってからは、どういうセクシャリティだろうがそこに上も下も何もないし、みんなが〈GUCCI〉を好きになってくれればいいじゃんって感じになりましたよね。〈adidas〉と一緒に着てもいいし、〈stussy〉と一緒に着ててもいいよ、みたいな。

フイナム:発売されたコラボレーションを見ても、歴然と違いますよね。

菅付:そう。トム・フォードの時代はゲイ的なセクシャリティを強く打ち出して、すごくエロティックでちょっとスノップで選民的で、ダサいやつは絶対お断りみたいな感じだったわけじゃないですか。ミケーレのときは〈adidas〉のジャージを履いて、上に良かったら〈GUCCI〉のジャケットを着てよ、みたいな感じですよね。

長谷川:(笑)。僕は会ったことないんですけど、ミケーレさんってすごくいい人らしいですね。昔、友達が下北沢を案内してあげてたそうです。
時代の転換点。

菅付:そんな風に〈GUCCI〉を例にしても、やっぱり時代の価値観は変わりましたよね。トム・フォードのときはあれはあれで面白かったですけどね。トム・フォードは自分自身のブランドも売っちゃったし、ああいう美意識、時代がひとつ終わったんだなと思います。

長谷川:最近あんまり聞かなかったですもんね。トム・フォードの〈GUCCI〉とか〈YVES SAINT LAURENT rive gauche〉とか、かっこよかったですけどね。

菅付:よかったですよね。

長谷川:あの時代は他にも色々良かったんでしょうね。ラフ・シモンズとかヘルムート・ラングもいたりして。

菅付:そうですね。ひとつ言えるのは、ゲイの人たちが研ぎすまされた感性を示さないといけない時代でもあったと思うんですよね。ゲイという存在がマイノリティだからこそ、ある種のラウドマイノリティ(声の大きい少数派)というか、ちょっと強い美意識をより高級でエッジィなものとして出さなきゃいけない。けど、今はミケーレの例を挙げるまでもなく、そういったことはもう日常のなかのひとつですよね。

長谷川:確かに。そもそもほんの10年前までは、メンズファッションって基本的にゲイのものだったじゃないですか。

菅付:そうですね。

長谷川:だから例えばトム・フォードかどうこうっていう話を普通の人に話したところで、まったく理解されなかったですよね。でも今やそういうことが普通の人との会話でも出せるような感じになりました。それが変わったのって本当この10年くらいですよね。価値観が一変した。

菅付:そう思います。

長谷川:それによってゲイが生きやすくなったんでしょうけど、もしかしたら生きにくくなったゲイもいるのかもしれないですね。

菅付:そうですね。かつてファッションにおけるゲイっぽさというのは、すごく目立つ強力なスパイスであり、ある種シグネチャーみたいなものだったんですよね。だからラグジュアリーブランドでもそういう服がたくさん作られていた。でもそれはLGBTQ的なものが、遠くの人の遠くの問題や遠くの価値観ではなくて、日常であり当たり前のことになった今とはまったく違う価値観に思えるわけです。
技術の世界。

菅付:一方で、デムナ・ヴァザリアは全然違うやり方をしていますよね。ハイ・アンド・ローをいかに激しくミックスさせるかというか。明らかにローなものと、明らかにハイなものをわざとぐしゃっとしてますよね。

長谷川:そうですね。それはそれで刺激的に見えるし、わかりやすいですよね。

菅付:彼はパリで生まれ育った人ではなく、東欧ジョージア出身で大学もアントワープのロイヤル・アカデミーだから、パリの本流と違うことをやろうということですよね。というかパリの本流は彼のなかにはないわけなので、逆に思い切ったことができますよね。パリにいるとパターンとかをしっかり勉強するだろうし、クチュリエのことも考えると「これはちょっと難しいだろうな」と思ったり。クラシックを勉強しすぎた音楽家がわりと無難な曲しか書けない、みたいなことに通じるというか。そういう意味ではデムナ・ヴァザリアはファッションの外から来てるからこそ、思い切ったことができるし、あとはそれを〈BALENCIAGA〉が後押ししていることも大きいですよね。

長谷川:たしかに。そう思うと〈BALENCIAGA〉ってすごいですよね。

菅付:最近色々問題があったので、これからどうなるかはわからないですけどね。いろいろな意味で、今はファッションの大転換点であることは間違いないですね。ファッションの歴史のなかで、ラグジュアリーが黒人のカルチャーを急速に取り入れて、さらにそういう客も取り入れようとして、それがすごくうまくいっていたんですよね。さらに「ブラック・ライヴズ・マター」が後押しをして、ああいうカルチャーや人を応援することがポリティカル・コレクトネス(政治的な公平さ)になったんですけど、やっぱりちょっと行き過ぎた部分もあって。

フイナム:というと?

菅付:ここ数年の「ブラック・ライヴズ・マター」運動の影響で、欧米のファッション誌では黒人のカメラマン、黒人のモデルがどっと増えましたよね。それがみんな素晴らしい才能の持ち主であればいいんですけど。タイラー・ミッチェルのようなスター性も才能もある黒人の若手写真家が脚光を浴びているけれど、それほど特徴のない黒人の若手写真家も続々と起用されたりしている。人種バイアスが逆張りになってるんです。

長谷川:なるほど。

菅付:とにかく黒人のクリエイターを全面にプッシュしようというポリティカル・コレクトネスが一気に盛り上がった後に、ヴァージル・アブローが亡くなって、カニエ・ウエストが〈adidas〉や〈BALENCIAGA〉から離れて、この後どうなっていくのかという感じですよね。

長谷川:ヴァージルは黒人たちの間ではやっぱりスターだったと思いますし、それこそマイケル・ジョーダン以来の人だったのかもしれないですよね。でも、なんかこのねじ曲がった感じってありますよね。もうちょっと素直なところで物事が動いてくれるといいんですけどね。

菅付:そう思います。ファッション業界はマーケットが大きくなった部分、ポリティカル・コレクトネスに関して過剰に気にするようになって、そうなってくると「この写真家がいい」とか「このモデルがチャーミングだ」というのとは違う判断が働いていて、それはやっぱりここで訂正された方がいいと思いますね。結果的に「いいなと思う写真家がたまたま黒人だった」というのが、いいわけじゃないですか。

長谷川:それはありますね。この業界は基本的には技術の世界ですからね。最近その話があんまり語られてない気がするんですよね。鮨屋とかと同じで、いかに技術が優れてるかによって作品の良し悪しが変わるわけで、それが例えば人種を理由に優先されるみたいな話になっちゃったら、もう何が正しいのかわからなくなってしまうので。

菅付:その通りですね。だからそろそろ揺り戻しが来ると思いますね。特定の人種を特別尊重も蔑視もすることなく、「人種はなんであれ、この人が一番旬な才能だから起用しよう」というところに。

長谷川:うんうん。そういうピュアな世界であってほしいですよね。