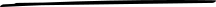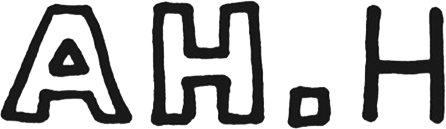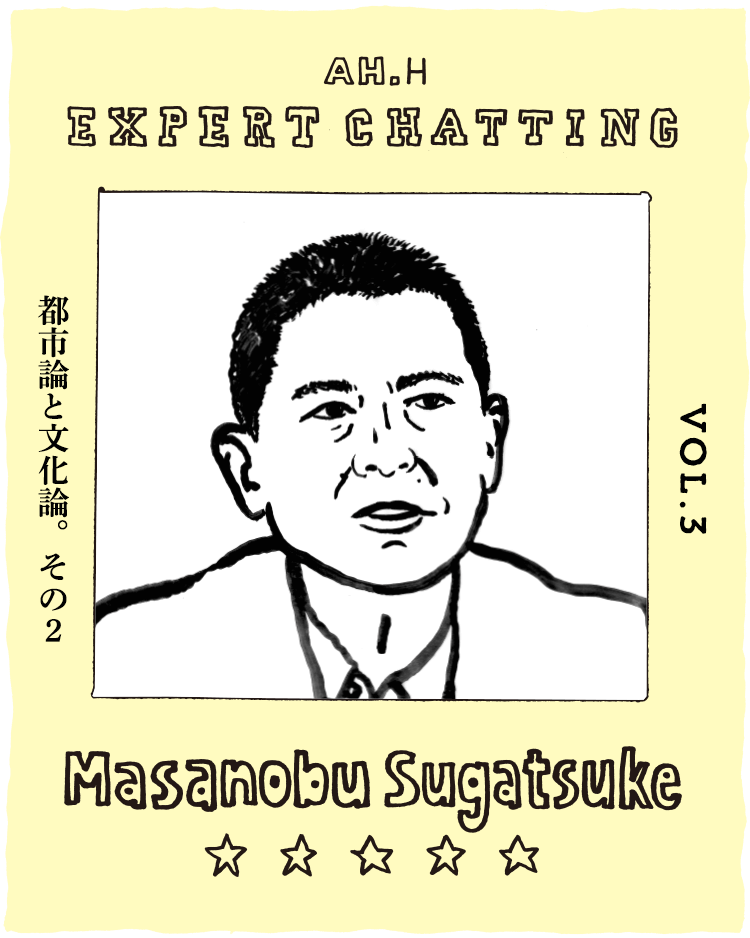PROFILE

編集者/株式会社グーテンベルクオーケストラ代表取締役。『コンポジット』『インビテーション』『エココロ』の編集長を務め、現在は出版物の編集・執筆から、コンサルティングを手がける。著書に『はじめての編集』『物欲なき世界』『動物と機械から離れて』等。下北沢B&Bで「編集スパルタ塾」、渋谷パルコで「東京芸術中学」を主宰。22年4月より東北芸術工科大学教授。NYADC銀賞、D&AD賞受賞。

ファッションディレクター、スタイリスト。英国の雑誌『モノクル(MONOCLE)』の創刊より制作に参画、ファッションページの基礎を構築した。2015年には同誌のファッションディレクターに就任。2012年から2018年秋まで雑誌『ポパイ』のファッションディレクターを務めた。
Chapter2
2022年のクリエイティブ論考。

フイナム:最近「コンデナスト」の体制が変わりましたよね。

菅付:もう、大変革ですよ。『VOGUE US』編集長のアナ・ウインターが全部見ることになったって聞きました。本当にそんなことができるのかはわかりませんが。各国に編集長=Editor in Chiefというポジションがなくなってしまったんです。

長谷川:へぇ、そうなんですね。

フイナム:アナ・ウインターって今おいくつくらいでしたっけ?

菅付:いくつだろう、70歳くらいかな(※1948年生まれで現在72歳)。昭雄さんは「コンデナスト」だと『GQ』とかやったことありますか?

長谷川:ものすごく昔にありますね。軍地(彩弓)さんが編集長になった頃に表紙を少しやらせてもらったり。あと亡くなってしまった竹内(大)さんと一緒に〈adidas〉のタイアップとか。けど、外からたまにやってたぐらいなので、会社の状況がどうだったかとかはわからないですけどね。

フイナム:『エスクァイア日本版』は結構やってましたよね。

長谷川:やってたね。うちの師匠(喜多尾祥之氏)がやってたからね。

菅付:僕は『エスクァイア日本版』の編集部に8ヶ月だけいたんです。当時の編集長と相性が合わなくて、すぐに辞めてしまったんですが。

長谷川:あ、そうでしたね。それにしても編集という職業は、本当に長く続けられる仕事ですよね。

菅付:そうですね。『GQ』にいらした鈴木正文さんもたしか72~3歳くらいですし(※1949年生まれで現在73歳)。

長谷川:ファッションの仕事って日本ではそこまで歴史がないですけど、欧米のことを考えると、それくらいの年齢まで普通にできるわけですもんね。

菅付:だってジョルジオ・アルマーニっていまいくつですか?

フイナム:80歳はとっくに超えてますよね。

菅付:85歳とか?ですよね(※1934年生まれで現在87歳)。ソニア・リキエルが亡くなったのも、確かそれくらいでしたよね(※86歳で没)。

長谷川:へぇ。

菅付:クリエイティヴの仕事、とくに視覚系、ビジュアル系の仕事は、本人のやる気と努力しだいではあるんですが、すごく長くやれるんだと思います。というのも世の中の見た目と、自分の見た目を気にする仕事じゃないですか。外見、アウトルックに無自覚な人はできないですよね。例えば、操上和美さんの若さってすごいじゃないですか。

長谷川:あぁ、たしかに。鍛えてますもんね。

菅付:今、86歳ですよ! 週2で「トータルワークアウト」に行ってトレーニングしているし。僕、一度操上さんのトレーニングを見せてもらったことがあって。

長谷川:そういえばさっき話した『GQ』の表紙は、フォトグラファーが操上さんでしたね。姿勢が良くて、言うこともビシッとしているというか、シャープでしたね。クリエイティブってやればやるほど、どんどんシャープになるようなところってあると思うんですよね。若いときには思いつかないようなことが、年をとってできるようになったり。感性って若い人にしかないと思われているようなところがあるんですが、意外とそんなことはないと思うんです。

菅付:そう思います。

長谷川:人生経験がプラスになるというか。でも、みんなあまりそういうふうに思ってないですよね。
文脈の重要性。

フイナム:菅付さんは若いクリエイターともベテランのクリエイターともお仕事されるんですか?

菅付:なるべく意図的にそうしようと思っています。若いときはなんにも知らないじゃないですか。知識も経験もないし。だったら色々知っている人と仕事した方が勉強になりますよね。この仕事をやっているとわかるんですが、どの分野にも絶対に上には上がいるじゃないですか。写真でもスタイリングでもグラフィックでも。そういう人を見ると「あぁ、まだ学べるな」と思うんです。そういう姿勢は僕はわりと大事かなと思うんです。もちろん上の人と仕事するとすごく大変なんですけど。

フイナム:本当そうですよね。

菅付:一方で常に若いクリエイターとも仕事をしたいなとも思います。これはもうはっきりと言葉にして言っているんですが、中堅とはあんまり仕事をしたくないんです。勉強にならない気がして。上には上の人と、または若いフレッシュな人と仕事をしたい。そういう意味で、昔から同年代からはすごく嫌われているんです。

長谷川:笑

菅付:でも、同年代と仕事をする方が楽だし、楽しいですよ。それはそうなんですけどね。僕は本をつくるのも、老人と若い人の本ばっかりです。僕が編集して初めて本を出しましたという人が半分くらいで、あとは老人ですね。例えば初めてのマーク・ボスウィックの写真集とか世界で初めてのエリザベス・ペイトンの画集とか、こないだ木村伊兵衛賞をとった片山真理さんの初の写真集とか、画家の武田鉄平の初画集とか。まだ誰も声をかけてないような人、新しい才能と一緒に仕事をすると、すごく刺激になりますね。

長谷川:編集の仕事っていうのは、そういうキャスティングが重要ですよね。

菅付:キャスティングが9割ですよね。キャスティングさえしっかりしていれば、極端な話、自分がそんなに動かなくてもどうにかなりますけど、キャスティングがガタガタだったり、なんか合ってない人と組んじゃうと、すごく考えてすごく準備しないといけないので。それでもあんまりうまくいかなかったりしますね。

長谷川:そうですよね。でも、新しい人とやるときって、結構大変ですよね。その人の作品は好きでも、なんか性格が合わないみたいな(笑)。編集だとそういう立場に立たされることって多くないですか?

菅付:そうですね。編集者はある種のゲロ袋みたいなもので(笑)。周りのスタッフやクライアントのいろんな不満とか怒りを吐きかけられたりするわけです。

長谷川:笑

菅付:これらをうまく自分のなかで濾過して形にしていくしかないんですよね。

長谷川:はけ口みたいなことですよね。

菅付:結構ひどいこととか言われましたね。とくに外国人クリエイターとか平気でひどいこと言うんです。昨日まで機嫌いいこと言ってたのに、今日は全然違うみたいな。まぁしょうがないなって感じですけどね。

長谷川:もう慣れっこですか?(笑)

菅付:いやぁ、慣れたいけど、やっぱり心は痛みますよね(笑)

長谷川:新しい人は探すのはくせのような感じなんですか?

菅付:新しい才能に出会ってないと、自分が新陳代謝できないですよね。自分の人やモノを見る目というか、審美眼が落ちてきますから。「目がいい」というのは、英語でもそういう言い回しがあるんですが、目がよくないとクリエイティヴの仕事はだめじゃないですか。カメラマンのポートフォリオを二つ見て、どっちがいいかってぱっとわからないとダメだと思うし、そのためにはずっと見てないとわからなくなるんですよね。

長谷川:本当そうですね。

菅付:例えば一年間山奥にこもって、外界とシャットアウトして、文章を書いたり絵を描いたりしたあとに、新人カメラマンのブックを見たって、絶対わからないと思うんです。

長谷川:それはやっぱり人に接してないと、ってことですか?

菅付:というより、新しさは結局、文脈的なものだと思うんです。古っぽいものが新しく見えるときは、文脈的な判断じゃないですか。それこそファッションのサイズ感とかそうですよね。ぴたっとしているものがいいなというときもあれば、大きいものが今だなと思うときもあるわけですが、それって形そのものがいいというわけではなくて、流れのなかのことだと思うので、流れがわからなくなったら、もう判断できないですよね。

長谷川:たしかにそうですね。以前、いつも書いている原稿の英語版を作りたいと思ったことがあったんです。で、英訳してみていろんな国の人に見てもらったんですけど、みんなが言ってたのは、そもそも日本語を英語にするのってとても難しいっていうこと。あと、お前の書いている原稿は専門的すぎてよくわからないって。全然そんなつもりはないんですけど、多分文脈なんですよね。文脈がわからないと、わからないんだと思います。

菅付:はい。とくにファッションは猛烈に文脈的な領域なので。

長谷川:技術があっても使い方がわからないというか。

菅付:そう、とくにここ20年くらいはファッション写真はヘタウマにいったり、そうでないほういったりの繰り返しじゃないですか。例えばスティーブン・マイゼルとかデヴィッド・シムズなんて、時々すごくリアルでハイパーでパキっとしたものをやったり、逆にヘタウマをやったりするじゃないですか。もしくはそれを組み合わせたりとか。彼らは文脈を読む天才で、両方できてしまうし、自由自在に対応できる。とにかくファッションにはつねに波があるから、そういうのをわかってないと、今のファッション写真は撮れないですよね。
情報過多時代において。

フイナム:長谷川さんは、例えば写真集などをリファレンスにしたりしないですよね。

長谷川:あんまりしないね。まぁ、した方がいいんだろうけどね(笑)。だんだん自分の表現の仕方っていうのが、微妙な数センチの幅のなかで動かすようになってきてて。ただ、それをやるうえでも、いろんな情報を入れてやった方がいいのかもしれないんだけど、今って情報が多すぎて咀嚼するのが大変だから、あえて入れないっていう道を選んでしまっているのかも。

菅付:それはありますね。間違いなく今は情報過多だから、ある種自分にとっての定点観測的なお店とかメディアとか人が大事になってきてますよね。それらをベンチマークして、「この人が言うなら信用できる」という風になってきていると思うんです。

長谷川:そうですね。けど、さっきも言ったんですが、本当は情報をある程度入れながらやったほうが、作るもののグレードが上がっていくっていうのはありますよね。もう全然本屋とか行かなくなっちゃいましたね。。さっきも代官山の蔦屋書店に行ったんですけど、こんなに雑誌あるんだなって思ったりして(笑)。

菅付:笑

長谷川:みんないろんな写真撮ってるんだなって(笑)。ただ僕に関して言うと、アート的な世界からはどんどんかけ離れてきているというか、もっと下世話なところでやってきてるところがあるので、そういうものがあんまり必要ないといえば必要ないのかもしれないです。ただファッションの本来のシーンっていうのは、そういうところですからね。もうちょっとアート的な部分っていうのは必要なのかもしれないですね。

フイナム:長谷川さんが、生活する上で今を感じる部分って、どういうところですか?

長谷川:今、自分が生きているっていうところで、今を感じているだけかも。だんだん誰もが自分のなかだけで完結し始めちゃっているのかもね。だからインスタも世界とつながっているようで、自分の世界でしかない。意外と狭い世界なんだよね。

菅付:そうですね。インスタでもなんでも自分がフォローしている人の情報が質が高くて、信用できるようなものであればいいと思うんですが、そうでないと結構まずいですよね。アメリカのトランプ支持者のfacebookを分析した記事があって、彼らが見ている情報ソースが猛烈に偏ってたんです。CNNとかニューヨークタイムズとか、そういった主流の報道メディアの情報が恐ろしくなかったようなんですね。

フイナム:そうなると陰謀論じゃないですが、どんどん極端に偏ってきますよね。

菅付:そう。怖いですよね。

長谷川:政治的な操作をなにかされているかもしれないですもんね。僕は、同じチームで撮影をすることが多いんですが、たまに役者とか音楽関係の方とお話しすると、刺激になります。そういう考え方もあるんだなというか。今回のように菅付さんとお話することもそうなんですが。ファッションの世界だけのものの見方ってやっぱり狭いですし、僕の場合はファッションのなかでも更に狭いので、違う世界からの情報が入ると面白いなって思います。
拡張していくファッション。

菅付:今はどこまでがファッションなのかっていうのが、曖昧になってきていますよね。例えば〈snow peak〉ってファッションブランドなのかってなると、いろんな捉え方がありますよね。〈THE NORTH FACE〉とかも。

長谷川:昔は〈NIKE〉も、自分たちはスポーツブランドだって頑なに主張して、ファッション的な見せ方はしないでほしいって言ってましたけど、いまや全然そんなことないですよね。スポーツなのかファッションなのかわからないというか、自らファッションの方にアプローチしてきていますよね。僕はスタイリストなので、初めからそういうのを崩して見ているところがあるんです。だから〈寅一〉みたいなものでも〈UNIQLO〉でも〈LOUIS VUITTON〉でも、全部同列で見たいっていう意識がずっとあります。でも、今って普通の人でもそういう感じになりつつあると思うんです。あえて〈UNIQLO〉を合わせることでドキドキするっていうような人はおそらくいないですよね。あれが普通だと思うから買うわけで。

菅付:日本のファッションメディアのスタイリングは、すごく優れたところがあるなと昔から思っているんです。東京は世界のファッション・キャピタルのひとつだとは思うんですが、どこが中心かっていったら、それはいまだにパリだと思うんですね。そういう意味ではパリから見たら日本はファッションの周縁の場所なので、だからこそ本場に対して何をやってもいいみたいなところが昔からあったと思うんです。だから〈LOUIS VUITTON〉と他のカジュアル系ブランドを平気で混ぜちゃうとか、そういうことをやってた。そういう乱暴なやり方は、東京とあとはロンドンが生んだものだと思うんです。

長谷川:あー、なるほど。

菅付:そう、ロンドンは『i-D』とかがあったので、やっぱりパリとは違うんですよね。ファッションの本場ではないんです、ロンドンは。『VOGUE PARIS』を見ると、本場の雑誌だなという感じですよね、つねに。一方で初期の『i-D』にラグジュアリー・ブランドは出てこなかったけど、次第に登場するようになってきて、そこにワークブーツや〈Dr Martens〉を合わせたりしていましたよね。今になれば全然珍しいことではないし、そもそも今や本家がそれっぽいものを作るようになりましたよね。あれは元々80年代の東京とロンドンが産んだスタイルですよね。ファッションの中心じゃないからこそできたことというか。

長谷川:そうですね。たしかにロンドンの影響なんでしょうね。

菅付:あとヨーロッパの場合は、ブランドと階層(クラス)がはっきりしてるじゃないですか。〈HERMES〉を普段買っている人は、そういう階層にいるわけです。彼らは暗黙のうちに、服の文脈と階級の文脈がわかっているんですよね。日本人は良くも悪くもわかってない。ブランドの階級的なものをあまり意識してないので、いい意味で誤解して混ぜられるんですよね。わざとひんしゅくを買うくらい混ぜてクラス感をぐしゃぐしゃにしていくというか。そういうことをやってきた歴史がありますね。それはオリジナルなスタイルだし、考え方でしたよね。パリの人は階級をあまりにわかっているから混ぜられないんですよね。〈HERMES〉と〈Gap〉を一緒に着る人がいないわけなので。

長谷川:そうですね。けど、もはやそういうことを思わないぐらい、今は普通ですもんね。今もパリはそんな感じなんですかね。

菅付:パリの人たちも頭がいいので、今の時代、例えば「スポーツ的な要素を混ぜないといけないんだな」というようなことはわかってると思います。だからどこのラグジュアリー・ブランドでもスニーカーをたくさん作ってますし。ハイヒールをやめることはないけど、今はハイヒールですごく稼ごうとは思ってないですよね。

長谷川:たしかに。けど、ブランドもののスニーカーって、なんかやっぱり抵抗があるんですよね。。

菅付:僕もあれ大っ嫌いです!(笑)。すごく中途半端だし、機能的でもないし。もうちょっとそういうことをファッションメディアも言った方がいいと思うんですよ。

長谷川:なんか説得力に欠けるかなって思ってしまって。男の人のワードローブにおける靴って、その人のセンスをわかりやすく示すものだから、すごく大切だと思うんです。服ほどはブランドの数が多くないので、見てすぐにどこの靴か、だいたわかるから、こういう服装にはどういう靴であるべきか、だいたい想像つくわけじゃないですか。それが予想と大きく違ってくることがいいこととは僕は思えないんです。おしゃれな人はそこを裏切るような靴を履いていることはまずないですから。

菅付:本当そうですよね。

長谷川:革靴ならわかるんですが、スニーカーってなると。。スニーカーも含めて、靴の専門ブランドは、靴専業だけに、履き心地もデザインも超一流なわけじゃないですか。例えば〈NIKE〉だけで言っても、マイケル・ジョーダンがそれを履いてプレイしてチャンピオンを争ったりするくらいのレベルですからね。他の競技や選手においても同じことが言えるわけで。。そうなると、わざわざ洋服ブランドで買う意味を見つけるのは、僕個人としては、なかなか難しいと感じてしまうんです。あ、でも他人が履いてる分にはなんとも思わないですよ。そういうのが好きな友達もいるし、とがめるつもりはないです。好きな物を履けばいいと思ってますから。あくまで自分の話です(笑)。

菅付:僕はどう考えてもちゃんと走れなそうなラグジュアリーのスニーカーって、カッコ悪いと思うんですよね。

長谷川:そうですね。例えば〈New Balance〉みたいなものを作ってるブランドもありますけど、だったら〈New Balance〉を買うしっていう。そういう意味でも文脈が大事というか。