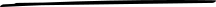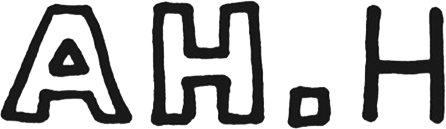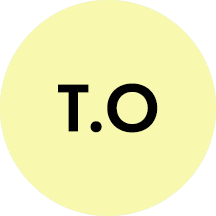
1966年愛知県生まれ。1992年にファッション業界紙の繊研新聞社に入社。1995年から欧州メンズコレクション、2002年から欧州、NYウィメンズコレクションの取材を担当し、およそ30年間、世界中のファッションを取材、執筆している。

フイナム:今回「AH.H」として初めてピッティに参加させていただいたのですが、この記事では、ピッティを長年取材し続けてこられている『繊研新聞』の小笠原拓郎さんにお話を伺いながら、あらためてピッティを振り返っていきたいと思います。
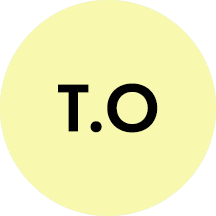
小笠原:よろしくお願いします。

長谷川:小笠原さんは、もう何十年もコレクションやショーの取材をされているんですよね?
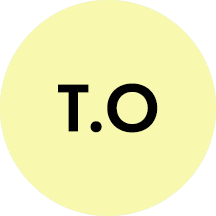
小笠原:そうですね。コレクションの取材は30年くらいやってます。

長谷川:僕はコレクションってほとんど行ったことがないんですけど、僕が以前働いていたようなファッション誌の編集長って年を追うごとに変わっていくので、ずっと見続けている方ってあんまりいないですよね。
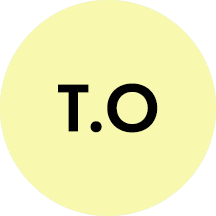
小笠原:スタイリストで長年通い続けている方もいますけど、周りを見渡しても、一番長くなってしまったかもしれないですね。



長谷川:今回ピッティでお話しさせていただいて感じたんですけど、小笠原さんって他の方々と、見ることの意味というか、視点が全然違いますよね。
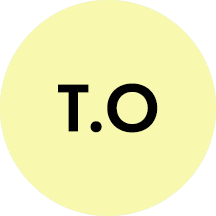
小笠原:そうかもしれないですね。

長谷川:そういう小笠原さんの視点から見たピッティとはどんなものなのかを伺いたくて、今回お声がけさせていただきました。
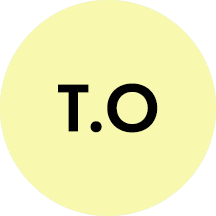
小笠原:ありがとうございます。だいたいこれは見ておこうというブースが自分のなかにあるんです。ピッティって、テーラリングの傾向が一番わかりやすい展示会なので、ここを見ておけば次のシーズンのテーラリングの素材感とか色なんかは大体掴めるんですよね。ただ、コロナ以降はクロージングのマーケットが縮小してしまったので、そういう意味ではピッティを見る視点も変わってはきています。

長谷川:そうですよね。

「PITTI IMMAGINE UOMO 108」のテーマは「BIKES」。前回は「RUNNING」がテーマということで、近年の「PITTI IMMAGINE UOMO」はファッションと異なるファクターの掛け合わせに意欲的だ。
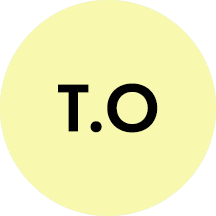
小笠原:女性のファッションって、パリコレクションのプレタポルテのブランドがトップオブトップだと思うんです。だからそういうブランドをどんな風に揃えるかというのが、お店にとってはすごく大切なんですよね。でも男性のファッションって、パリのメンズコレクションに出ているブランドがマーケットのメインではないですよね。それよりも、クロージングがマーケットの重要な位置を占めていたわけなので、そういう意味でもピッティが担っていた役割というのは大きかったんです。

長谷川:なるほど。
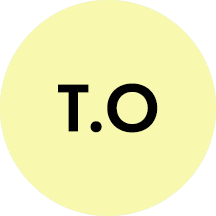
小笠原:それがコロナの影響でリモートワークが増えたこともあって、ビジネスウェアとしてスーツを着る機会というのが減りました。もちろん着飾るためのクロージングというのはまだ残っているんですが。


フイナム:クロージングのブースは、昔と比べるとだいぶ減ったそうですね。
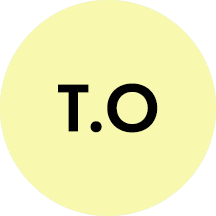
小笠原:そうですね。だから、どのブランドもいわゆるトータル化をしようとしています。

長谷川:たしかに。パンツ屋がシャツを作ったりしていますよね。
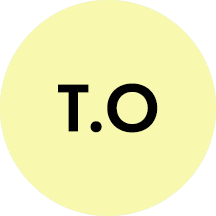
小笠原:そうです。テーラリングがメインだった企業が、カジュアルなものを作るようになっているのが最近の傾向ではありますね。とは言っても、数は少ないながらもテーラリングをメインにしてピッティに出続けている企業もあるので、それらを取り上げることはピッティの取材としてはすごく大事にしています。

長谷川:とくにここは、というブランドはありますか?
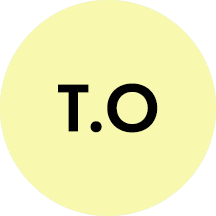
小笠原:例えば〈Belvest〉とか。〈Belvest〉はすごく優秀なファクトリーでもあるので、パリのいくつものラグジュアリーブランドのアイテムを作っていて、とくにダブルフェイスのコートなんかは得意ですよね。そういう“手”があるところなんです。あとは〈Brunello Cucinelli〉ですかね。

フイナム:〈Brunello Cucinelli〉はすごく広いブースでしたね。人もすごく多かったです。
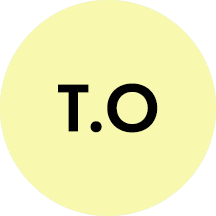
小笠原:そういうブースを見て、素材感とか色の感じがどうなのかというのを見たりします。26SSシーズンは、コーラルピンクなど赤っぽい感じの色が多かったように思いました。それが今のテーラリングのひとつの流れなのかもしれないですね。

長谷川:〈Brunello Cucinelli〉って、ヨーロッパにおいて圧倒的に認知されていますよね。ものすごく高級なブランドなのにすごいですよね。
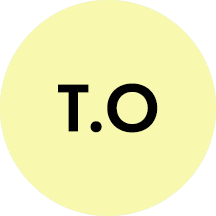
小笠原:以前、ピッティ協会の方々に〈Brunello Cucinelli〉がここまで大きくなったのはなぜだと思う?って聞かれたことがあるんですが、それはやっぱりストーリーじゃないかなって答えたんです。

フイナム:といいますと?
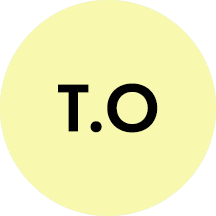
小笠原:〈Brunello Cucinelli〉は、ソロメオ村というイタリアの小さな村に繊維産業を復活させて、村に雇用を生み出し、ハンドクラフトの技術を守って、寂れた村を立て直していったというストーリーが背景にあるんです。今の時代、そういうストーリーをみんな欲するじゃないですか。

長谷川:たしかに。
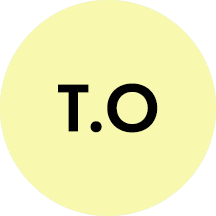
小笠原:最初にアメリカ西海岸のお金持ちにどかんと受け入れられて、一気にブームになったんです。

長谷川:なんかわかる気がします。
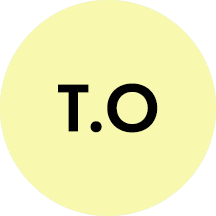
小笠原:ちなみに、創業者のブルネロ・クチネリさんという人は、いわゆる大量生産、大量消費ではなくて、“人間的資本主義”みたいなことを言っている方です。手で作る文化を大事にして、持続可能なビジネスを作っていくという、サステナブルの考え方をすごく早くから取り入れていて、そういう意味での先見性はすごくある方だと思います。









フイナム:カジュアルなブランドでいうと、〈HERNO〉のブースもすごく大きかったですよね。

長谷川:そうだね。イタリアの人って、ナイロン系のアウターが結構好きなイメージがあるんだよね。

フイナム:〈STONE ISLAND〉とか。

長谷川:そうそう。いま日本でもすごく人気あるよね。
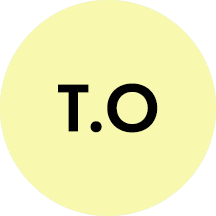
小笠原:僕が高校生ぐらいのときには、イタカジブームみたいなものがありました。

長谷川:僕より少し上の世代のお話ですね。
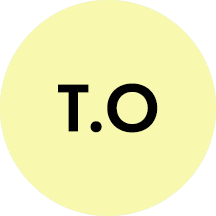
小笠原:思えば、その頃からイタリアってそういう系のアイテムが強かった気がしますね。

長谷川:〈STONE ISLAND〉とか〈C.P. Company〉に関して僕がよく覚えてるのは『id』とか『FACE』に入ってた広告ですね。だいたい90年後半から2000年代前半にかけてだと思います。

フイナム:ところでイタリアって、国の産業として服飾とか繊維をきちんと保護していたりするんでしょうか?
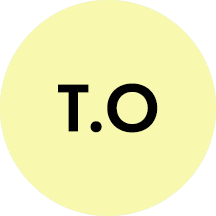
小笠原:国というよりも、そういうことに努力をしている企業はありますよね。例えば〈Brunello Cucinelli〉は〈CHANEL〉と共同で、イタリアの有名なカシミヤのファクトリー(※カリアッジ社)の株式をおよそ過半数ほど取得しているんです。

長谷川:その話、聞いたことあります。
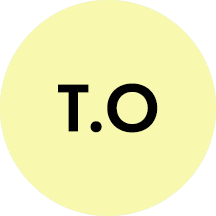
小笠原:そんな感じで、工場とかメーカーの手仕事を保護して、ものづくりを支えるような動きをしている企業はいくつかあると思います。

フイナム:近年、日本でもそういう動きは見られますよね。